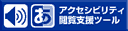よくあるご質問(ハローワーク求職情報提供サービスについて)
ハローワーク求職情報の提供サービスの利用団体(民間職業紹介事業者等)ご担当者様
ハローワーク求職情報の提供サービスの利用団体(地方自治体等)ご担当者様
ハローワーク求職情報の提供サービスを利用する求職者様
| Q5. | 対象団体等から不必要な案内送信が送られてきて困っています。防止(ブロック)する方法はありますか。 |
|---|---|
| A5. | 求職者マイページに不必要な案内等が送信されてきた場合は、その対象団体等からのメッセージをブロックする設定を行うことが可能となっています。詳しくは、求職者マイページ利用者マニュアル(利用登録者)「6.5 メッセージをブロックする」をご覧ください。 |
その他
| Q1. | 本サービスを利用するに当たり、特別なソフトウェアをインストールする必要はありますか。 |
|---|---|
| A1. | 特別なソフトウェアのインストールの必要はありません。 ただし、システム・セキュリティ確保のため、アンチウィルスソフトウェアの不正プログラムの提供ファイルを常に最新の状態に維持し、不正プログラムの自動検査機能を有効にしておくことが必要です。 |
| Q4. | 案内送信等できる件数は、総数で1日1,000件を上限とされています。同じ事業所・自治体内の部署ごとで申請していた場合でも、1事業所・自治体で1日1,000件でしょうか。それとも申請したそれぞれの部署で1日1,000件でしょうか。 |
|---|---|
| A4. | 上限数は利用団体単位となりますので、申請したそれぞれの部署で1日1,000件となります。 |
| Q5. | 利用者とトラブルになりました。どこに相談すればよいでしょうか。 |
|---|---|
| A5. | 個人情報管理・苦情処理責任者がきちんと対応するとともに、必要であれば最寄りのハローワークの苦情申出等受付担当者あてにご相談ください。 |
| Q9. | ワンタイムパスワード認証とは何ですか。 |
|---|---|
| A9. | 複数の認証要素を使うことでセキュリティを強化する認証方法です。求職情報提供サービスのログイン時、ID/パスワードに加え、一回限り有効なワンタイムパスワードを組み合わせて利用します。 |
| Q10. | 求職情報提供サービスにログインする際、ワンタイムパスワードはどのように送られてきますか。 |
|---|---|
| A10. | アカウントとして登録されたメールアドレス宛に、ワンタイムパスワードが記載されたメールが送付されます。 |
| Q11. | 求職情報提供サービスにログインする際、ワンタイムパスワードはどの端末で認証できますか。 |
|---|---|
| A11. | ハローワークインターネットサービスを利用可能なPC、スマートデバイス(スマートフォン、タブレット)で認証できます。 |
| Q12. | 求職情報提供サービスにログインする際、ワンタイムパスワードを発行しましたが、有効期間の30分間を過ぎてしまいました。どうすればよいですか。 |
|---|---|
| A12. | ワンタイムパスワード入力画面を閉じて、ログインからやり直してください。 |
| Q13. | 求職情報提供サービスにログインする際、ワンタイムパスワード入力をする前に、ワンタイムパスワードの通知メールを削除してしまいました。どうすればよいですか。 |
|---|---|
| A13. | ワンタイムパスワード入力画面を閉じて、ログインからやり直してください。 |
| Q14. | 求職情報提供サービスを利用していましたが、メールアドレスが利用できない(キャリア解約等)状況になりました。ログインできない状況でワンタイムパスワードが届くアドレスを変更することは可能でしょうか。 |
|---|---|
| A14. | 求職情報提供サービスにログインする前に利用者にてワンタイムパスワードが届くアドレスを変更することはできません。アドレスの変更が可能かどうか、労働局担当窓口にご相談ください。アドレス変更の手続きには日数がかかる場合があります。 |
| Q18. | ワンタイムパスワード省略設定の有効期間の残日数を確認する方法はありますか。 また、有効期間が切れる前に通知を受け取ることはできますか。 |
|---|---|
| A18. | 有効期間を確認する方法がないため、残りの日数を確認することはできません。 また、有効期間が切れる前の通知も行われません。 |
| Q19. | ブラウザのCookieを削除することで、ワンタイムパスワードの省略設定に影響はありますか。 |
|---|---|
| A19. | ブラウザのCookieが保持するワンタイムパスワード省略設定の有効期間を削除した場合、次回のログインにおいてワンタイムパスワードの入力が必要となります。 |
| Q20. | メインのアカウントと追加アカウントそれぞれ、ワンタイムパスワードでのログイン処理が必要でしょうか。 |
|---|---|
| A20. | 必要です。追加アカウントに紐づくCookieは、メインのアカウントとは別のCookieを発行するため、それぞれワンタイムパスワードでのログイン処理が必要となります。 |
| Q21. | メインのアカウントでワンタイムパスワード入力省略設定を行いましたが、追加アカウントでも省略を希望する場合は、追加アカウントで別に設定を行うことが必要でしょうか。 |
|---|---|
| A21. | 必要です。追加アカウントに紐づくCookieは、メインのアカウントとは別のCookieを発行するため、それぞれでワンタイムパスワード入力省略設定が必要となります。 |
| Q22. | 求職情報提供サービスにログインする際、ワンタイムパスワード入力の省略設定は、どのような仕組みで行っているか教えてほしい。 |
|---|---|
| A22. | 省略設定を行ったブラウザでCookieを保持し、次回以降のログイン時にCookie情報を確認することで省略可能か判定します。 なお、Cookieには、Cookieを識別するIDと有効期限の情報のみが記載されており、その他個人情報等を保持していません。 |
| Q25. | Cookieを有効にする方法を教えてください。 |
|---|---|
| A25. | Cookieの有効/無効の設定は、ハローワークインターネットサービス上ではなく、ご利用の端末において設定いただく必要があります。お手数ですが、各メーカーのサポート窓口等へお問い合わせいただきますようお願いいたします。 |
| Q26. | ワンタイムパスワードの仕組みは、どのような経緯で導入されたのか教えてください。 |
|---|---|
| A26. | ハローワークインターネットサービスのユーザセキュリティの向上を目的に導入されています。ID/パスワードに加えて、ワンタイムパスワードで本人確認を行うことで、第三者による不正なログインやなりすましを防止し、より安全に当サイトをご利用いただけます。 |